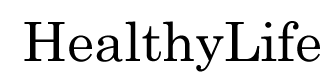「これって夢?現実?」― 親子で体験した不思議な感覚。その正体と、メモがもたらした驚きの効果

※ 本ページはプロモーションが含まれています。※ 他のトラブル解決も“ノジオ”で検索
「子どもの頃のあの思い出、本当にあったことだっけ?それとも、ただの夢だったのかな?」
ふとした瞬間に、自分の記憶の確かさに首をかしげた経験は、誰にでもあるのではないでしょうか。しかし、もしその感覚が頻繁に起こり、時には現実の会話で「話が通じない」という事態にまで発展したら…?
今回、ある読者の方から、非常に興味深く、そして切実なご相談をいただきました。
「うちの高齢の母親は、若いときから夢と現実の区別を見失う傾向があります。わたしも、子供の頃、考えていたことは、夢なのか現実に起こったことなのか分からないことがしばしばありました。現実に起こっていないことに対する考え事を人に話して、話が通じないようなことが起こりました。これは、精神的に病気の要素をはらんでいるのかとも思います。私は、社会人になって、こういうことでミスを起こさないようにメモを取るようにし出して直ったように思います。これは、どういう現象?」
親子で共有される、夢と現実の境界線が曖昧になる感覚。そして、「メモを取る」というシンプルな行動が、その長年の悩みを解決に導いたという事実。
この記事では、この不思議な現象の正体に、心理学や脳科学の観点から迫ります。そして、それが必ずしも「病気」ではない可能性や、誰にでもできる具体的な対処法、さらには同じような経験を持つ「みんなの声」をご紹介します。もしあなたが、自分の記憶の曖昧さに少しでも不安を感じているなら、きっとこの記事が、あなたの心を軽くする一助となるはずです。
夢と現実の境界線は、なぜ曖昧になるのか?
そもそも、なぜ私たちは夢と現実を混同してしまうことがあるのでしょうか。それは決して珍しいことではなく、私たちの脳の「記憶の仕組み」そのものに原因が隠されています。
1. 記憶は「再構築」されるビデオではない
まず理解すべきなのは、私たちの記憶は、ビデオカメラのように出来事をそのまま記録しているわけではない、ということです。記憶は、脳に保存された情報の断片を、思い出すたびに「再構築」するプロセスです。この再構築の過程で、私たちの感情、その後の経験、他人から聞いた話、そして「夢」で見た内容などが、無意識のうちに元の記憶に混じり合ってしまうことがあります。
特に、感情を強く揺さぶられるような鮮明な夢(Vivid Dream)は、現実の体験と非常によく似た形で脳に刻まれます。朝起きたときに「今のって夢だっけ?」としばらく呆然としてしまうのは、夢で体験した感情や感覚があまりにリアルだからです。
2. 子どもの脳と「現実検討能力」
相談者の方が「子供の頃に特にひどかった」と語っている点は、非常に重要です。現実と非現実を区別する能力は「現実検討能力(リアリティ・モニタリング)」と呼ばれ、主に脳の司令塔である「前頭前野」が担っています。
子どもの脳はまだ発達途上にあり、この前頭前野の機能も未熟です。そのため、豊かな想像力の世界と現実の世界との境界線が、大人に比べてずっと曖昧なのです。サンタクロースの存在を心から信じたり、空想の友達と真剣に会話したりするのも、このためです。感受性が豊かで想像力がたくましい子どもほど、自分の空想や夢を、現実の出来事として記憶してしまう傾向が強くなります。
3. 親子で似る「気質」という可能性
「母親も同じ傾向があった」という点も、示唆に富んでいます。これは、特定の病気が遺伝したというよりは、「物事の感じ方」や「考え方のクセ」といった気質が親子で似ている可能性が高いと考えられます。
例えば、
- 非常に豊かな想像力を持っている
- 感受性が強く、共感力が高い
- 内省的で、物事を深く考えるのが好き
こうした気質は、芸術的な才能や他者への深い思いやりにつながる素晴らしい個性です。しかし、その一方で、自分の内なる世界(思考や夢)に深く没入しやすいため、外的な現実との境界が揺らぎやすくなる、という側面も持ち合わせているのです。つまり、これは「欠点」ではなく、素晴らしい「個性」の裏返しと捉えることができるかもしれません。
「もしかして病気?」その不安に答える
夢と現実の混同が続くと、「自分はどこかおかしいのではないか」「精神的な病気なのではないか」という不安に駆られるのは当然のことです。
結論から言えば、この現象自体が、直ちに精神疾患を意味するわけではありません。
前述の通り、子どもの頃や、強いストレス、睡眠不足など、心身が不安定な状態では、誰にでも起こりうることです。
しかし、注意が必要なケースも確かに存在します。大切なのは、その「程度」と「日常生活への支障」です。
- 統合失調症: 妄想や幻覚(実際にはないものが見えたり聞こえたりする)が主な症状ですが、その初期段階で現実感が失われる感覚を覚えることがあります。ただし、鮮明な夢と妄想・幻覚はメカニズムが異なります。夢の混同だけでなく、明らかに非現実的なことを固く信じ込み、他者とのコミュニケーションが著しく困難になる場合は、専門家への相談が必要です。
- 解離性障害: 強いストレスやトラウマ体験をきっかけに、自分が自分でないような感覚(離人感)や、現実感がない感覚(現実感喪失)に陥ることがあります。記憶の一部が抜け落ちる「解離性健忘」もこの一種で、その空白を夢や想像が埋めてしまうこともあります。
- 高齢者の「せん妄」: ご相談にあった「高齢の母親」という点で、考慮すべき可能性の一つです。せん妄は、病気や薬、環境の変化などが原因で一時的に脳の機能が低下し、意識が混濁する状態です。幻覚を見たり、時間や場所が分からなくなったりするため、夢と現実の区別がつかなくなっているように見えることがあります。
重要な判断基準は、「その現象によって、仕事や人間関係、自己管理といった日常生活に深刻な支障が出ているか?」という点です。もし、生活が成り立たないほどの混乱や苦痛を感じているのであれば、一人で抱え込まず、精神科や心療内科といった専門機関のドアを叩く勇気を持ってください。
なぜ「メモ」は魔法の杖になったのか?
さて、この記事の核心とも言える部分です。相談者の方は、社会人になり「メモを取る」ことで、この長年の現象を克服したと言います。なぜ、このシンプルな行為がそれほどまでに有効だったのでしょうか。
1. 思考の「外部化」と「客観視」
私たちの頭の中は、常に思考、感情、記憶、想像が渦巻く混沌とした空間です。夢と現実が混同しやすい人は、この内なる世界の情報量が特に多く、整理が追いついていない状態と言えます。
メモを取るという行為は、この混沌とした頭の中身を、紙や画面といった「外部」に取り出す作業です。書き出された言葉は、もはや主観的な思考の渦の一部ではなく、客観的な「記録」に変わります。
「これは、実際に起こったことだ」
「これは、自分がこう考えただけのことだ」
書き出すことで、事実と意見、現実と想像を、自分の目で見て区別できるようになるのです。これは、まさに前述した「現実検討能力」を、メモというツールを使って補助・強化する行為に他なりません。
2. 書くことによる「思考の整理」
話が通じなかった経験は、「頭の中で整理されていない思考をそのまま口に出してしまった」結果かもしれません。書くためには、まず自分の考えを論理的に組み立て、言葉を選ばなければなりません。このプロセス自体が、ごちゃごちゃになった思考に秩序を与えるトレーニングになります。
「Aという出来事があった(事実)。それに対して、私はBと感じた(感情)。そして、Cかもしれないと考えた(推測)。」
このように、事実・感情・推測を分解して書く習慣をつけることで、現実の輪郭がよりくっきりと浮かび上がってきます。
3. 「やったこと」の確かな証拠
社会人になると、「言った・言わない」「やった・やってない」が大きな問題になります。タスクリストや議事録をメモすることは、まさに現実の行動を記録し、後から確認するためのものです。この習慣が、仕事上のミスを防ぐだけでなく、プライベートな記憶の確かさに対する自信にも繋がっていったのでしょう。メモは、不確かな記憶の海を渡るための、信頼できる「航海日誌」なのです。
みんなの声:「私もそうだった!」体験談
あなただけではありません。同じような感覚を抱えている人は、実はたくさんいます。
Aさん(20代女性)「私もです! 子どもの頃の記憶がすごく曖昧で、楽しかった家族旅行の話をしたら、姉に『え、そんなことあった? それ、あんたが見た夢じゃないの?』って言われることがしょっちゅうでした。想像力が豊かすぎて、頭の中で勝手に物語を作ってたみたいです。今は、それも自分の個性かなって思えるようになりました。」
Bさん(40代男性)「大きなプロジェクトを任されて、プレッシャーで眠りが浅かった時期がありました。その頃、朝起きるたびに『昨日クライアントに謝罪のメールを送ったのって、夢だっけ?現実だっけ?』って本気で焦ることが何度もありました。送信済みトレイを確認してホッとする、みたいな(笑)。やっぱり、睡眠の質と心の状態って直結してるんだなと痛感しましたね。」
Cさん(30代女性)「まさに、私が『メモ魔』です! ToDoリストはもちろん、打ち合わせ中の気づき、ふと思いついたアイデア、モヤモヤした気持ちも、全部スマホのメモアプリに書き留めてます。頭の中がクリアになるし、後から見返すと『ああ、この時はこう感じて、こう考えてたんだな』って客観的に自分を分析できるんです。事実と感情を切り分けるのに、すごく役立ってます。」
まとめ:個性を力に変えるために
夢と現実の境界線が揺らぐという、不思議で、時には不安になるこの現象。
その多くは、病気ではなく、記憶の仕組み、脳の発達段階、そして「豊かな想像力」や「鋭い感受性」といった個人の気質に起因する、ごく自然なものです。
相談者の方が見出した「メモを取る」という解決策は、単なるライフハックにとどまりません。それは、自分の内なる世界と客観的な現実とを区別し、思考を整理することで、自らの力で心の平穏を取り戻すための、非常に優れたセルフケアの手法です。
もしあなたが、かつての相談者の方と同じように、記憶の曖昧さに悩んでいるのなら、ぜひ今日からペンを取ってみてください。日記でも、箇条書きのメモでも構いません。頭の中にあるものを外に出し、自分の目で確かめる。その小さな習慣が、あなたの世界に確かな輪郭を与えてくれるはずです。
そして、忘れないでください。夢と現実を混同しやすいという特性は、見方を変えれば、誰よりもクリエイティブで、共感力に優れた人間であることの証かもしれません。その繊細な感性を弱点と捉えるのではなく、自分だけのユニークな「才能」として受け入れ、育てていく。
メモという羅針盤を手に、あなたの豊かな内なる世界の航海を、ぜひ楽しんでみてください。